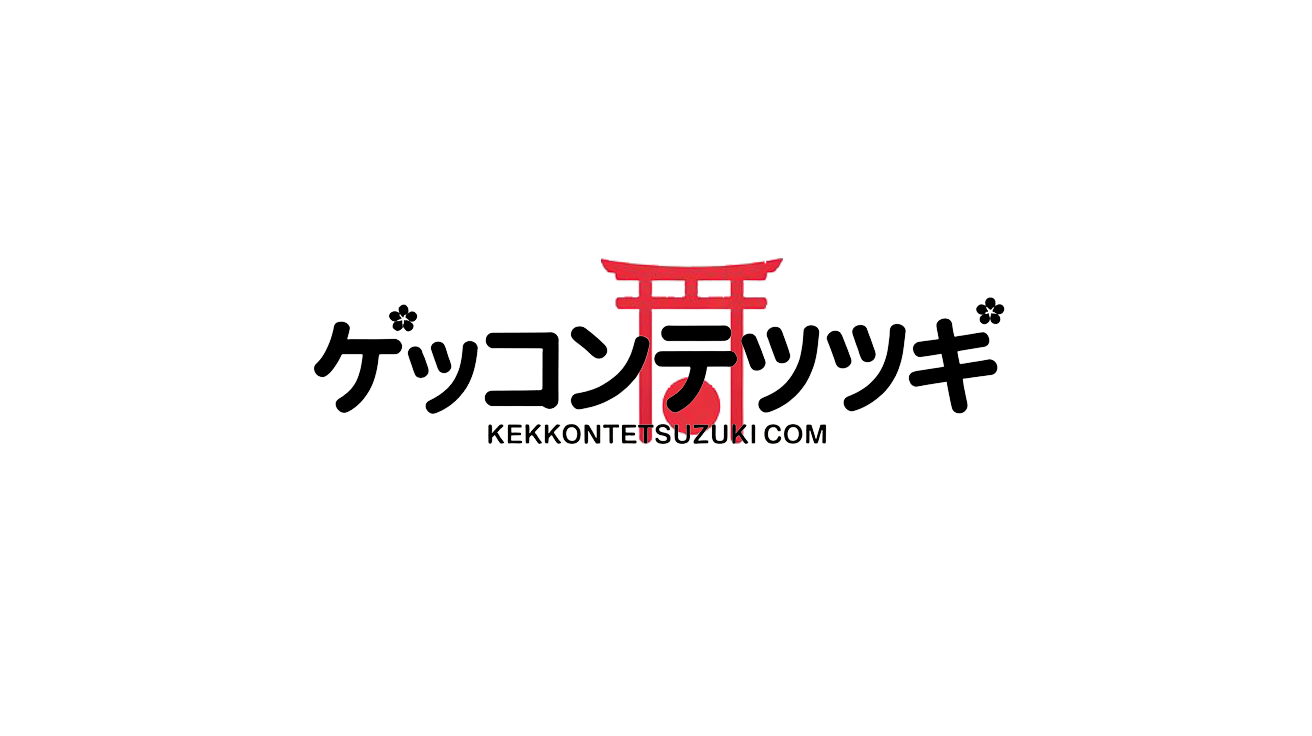シングルマザー(以下、シンママ)としての生活は、多くの挑戦と責任を伴います。その中で、新たなパートナーと事実婚を選択することは、家庭生活における新たな形態として注目されています。
本記事では、シンママが事実婚を選択する際の法的側面、社会的影響、経済的考慮事項、子供への影響、そして実際の体験談を交えて解説します。
事実婚とは?
事実婚とは、婚姻届を提出せずに、実質的に夫婦として共同生活を営む関係を指します。日本の法律上、事実婚は法律婚と同等の権利や義務が一部認められていますが、相続権などの点で差異があります。
シンママが事実婚を選択する法的側面
親権と戸籍
シンママが新たなパートナーと事実婚を選択した場合、子供の親権は引き続き母親が持ちます。新しいパートナーが子供を養子縁組しない限り、法的な親子関係は成立しません。また、子供の戸籍は母親と同じままとなり、パートナーとは別の戸籍に属します。
相続権
事実婚のパートナー間では、法律上の相続権が認められていません。そのため、遺言書を作成することで、パートナーに財産を遺す意思を明確に示すことが重要です。

社会的影響と認識
日本社会では、事実婚に対する認識が徐々に変化していますが、依然として法律婚が一般的とされています。シンママが事実婚を選択する際、周囲からの理解やサポートを得るためには、家族や友人とのコミュニケーションが重要です。
経済的考慮事項
公的支援と手当
シンママとして受け取れる児童扶養手当は、事実婚のパートナーと同居している場合、支給対象外となる可能性があります。これは、同居するパートナーが事実上の父親と見なされ、扶養義務があると判断されるためです。
税制上の扶養控除
事実婚のパートナーを税制上の扶養家族として申告することは認められていません。そのため、所得税や住民税の計算において、法律婚の夫婦と比べて控除額が異なる場合があります。note(ノート)
子供への影響
子供の福祉を最優先に考えると、新しいパートナーとの関係性や家庭環境の変化が子供に与える影響を十分に考慮する必要があります。子供の感情や意見を尊重し、適切なサポートを提供することが重要です。
実際の体験談
事実婚で子供を育てている家庭の一例として、以下のような体験談があります。この家庭では、父親が子供を認知し、健康保険の扶養に入れるなど、法律婚に近い形での生活を実現しています。しかし、相続権や税制上の扶養控除など、法律婚と異なる点については、遺言書の作成や適切な手続きを行うことで対応しています。
ヒントとアドバイス
1. 子どもとの関係を第一に考える
新しいパートナーとの関係を築く前に、子どもの気持ちや状況をしっかり理解し、信頼関係を保ちましょう。
2. パートナーとの価値観を確認する
子育てや家計管理など、家庭における価値観が一致しているかどうかを事前に話し合っておくことが大切です。
3. 法的な取り決めを明確にする
事実婚では相続や扶養の権利が限定されるため、遺言書の作成や養育費の取り決めを文書で残しておくと安心です。
4. 公的支援の条件を確認する
児童扶養手当や母子家庭支援など、同居パートナーがいることで受給資格が変わることがあるため、事前に調べましょう。
5. 周囲への説明と理解を得る
親族や友人など、近しい人たちに状況を伝えて理解を得ておくことで、サポートを受けやすくなります。
よく考えて決断しなければならない
シンママが事実婚を選択する際には、法的側面、社会的影響、経済的考慮事項、子供への影響など、多角的な視点から検討することが不可欠です。また、事実婚に関する最新の情報や制度の変更についても、常に注意を払うことが重要です。
非常に役立つ情報が掲載されている Web サイトへのリンク:
よくある質問
1. シングルマザーでも事実婚は可能ですか?
はい、可能です。法的な婚姻届を提出せずに同居・生活を共にする形で事実婚が成立します。
2. 事実婚でも児童扶養手当は受け取れますか?
同居パートナーがいる場合、扶養義務の有無にかかわらず支給対象外となることがあります。市区町村に確認が必要です。
3. パートナーが子どもの親権者になれますか?
法的には実子でなければ親権は持てません。必要に応じて特別養子縁組などの法的手続きを検討してください。
4. 事実婚のパートナーに相続権はありますか?
原則として相続権は認められません。遺言書などによって対応する必要があります。
5. 事実婚を証明するにはどうすればいいですか?
住民票に「未届けの夫(妻)」と記載されることで公的に認識されます。また、賃貸契約や生命保険の受取人登録も証明に役立ちます。